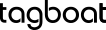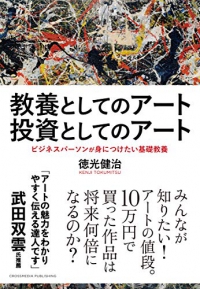日本のアート市場が育つために
少し前まで、どこに行ってもタピオカドリンクのお店が並んでいた。
黒くてプルプルしたあの粒を、太いストローで吸い上げるのが楽しくて、多くの人が並んで買っていた。
けれど、今はどうだろう。あれほどあったお店も、ずいぶん少なくなってしまった。
流行が終わると、まるで魔法がとけたように、人の関心は別のものへと移っていく。
では、アートもタピオカのように「一時的な流行」なのだろうか?
──答えは、もちろん「ノー」である。
アートは、人類がまだ言葉を話せなかった時代から存在していた。
壁に絵を描き、形や色で気持ちを伝えてきた。
それは、決してブームでは終わらない、人と心のつながりを表す大切な文化なのである。
お金持ちだけのものだった時代
戦後のヨーロッパやアメリカでは、アートはまだ一部の人のものだった。
お金持ちが画家に「この家に合う絵を描いて」と依頼して、自分の屋敷に飾る。そんな“オーダーメイド”のスタイルが主流だった。
このころ、アートは「買うもの」ではあっても、まだ「社会で流通する商品」としては育っていなかった。
「みんなで見る時代」のはじまり
ところが、1950年代から60年代にかけて、大きな変化が起きる。
アンディ・ウォーホルがスープ缶の絵を描き、「これはアートなの?」と問いかけるような新しい作品が登場した。
色や形の美しさよりも、「なぜこれを作ったのか」が重視されるようになったのである。
また、この頃から世界各地で美術館が増えはじめた。
アートは個人の家の中だけで楽しむものではなく、公共の場所で「誰でも見られるもの」になっていった。
さらに、美術を紹介するキュレーターや学芸員といった人たちが、作家の価値を社会に伝える役目を果たしはじめる。
アートが「見る人の知識」や「考える力」を育てるものとして、学校や社会でも重要視されるようになった。
市場としてのアート──投資の対象へ
1970年代から80年代にかけて、アートは少しずつ「資産」としても注目されはじめる。
誰が描いたのか、どんな評価があるのか、何年後に価値が上がるのか──そんな視点でアートを見る人が増えた。
この変化にともない、アート作品は「一度買ったら終わり」ではなく、「次の人に売ることができる」ものとしても扱われるようになった。
これが「セカンダリー市場」と呼ばれるもののはじまりである。
そして現代へ──生きている作家の時代
1990年代以降、アート市場はさらに大きく変化する。
これまでのオークションでは、亡くなった有名な画家の作品が中心だった。
しかしこの頃から、生きている作家──つまり「現代アート」の作家たちの作品が、オークションに出されるようになったのである。
さらに、2000年代にはSNSが登場し、アートのスピードが一気に加速する。作家が自分で作品を発信し、フォロワーと直接つながることで、ギャラリーを通さなくても人気が広がるようになった。
「いま注目されている作家」の作品が、何百万円、時には数千万円で取引される──そんなことが、もはや特別ではなくなってきたのだ。
タピオカは消える、でもアートは残る
ここで、もう一度タピオカの話に戻ろう。
タピオカは、確かに楽しくて、おいしくて、一時期とても人気があった。
けれど、それは“味”ではなく“流行”に支えられていた。そして流行はいつか必ず終わる。
でもアートはちがう。
アートは、人の心の中に何かを残すもの。時代をこえて、誰かの気持ちに届くもの。だからこそ、流行で終わることなく、文化として残り続ける価値があるのだ。
大衆化=価格を下げることではない
アートを「特別な人だけのもの」ではなく、「誰でも楽しめるもの」にする──この「大衆化」が、いま必要とされている考え方である。
だが、大衆化とは、ただ価格を下げることではない。
たとえば、寿司を思い出してほしい。昔は寿司といえば、ハレの日のごちそうだった。
けれど今では、回転寿司やチェーン店のおかげで、誰でも気軽に寿司を楽しめるようになった。
その一方で、職人がにぎる高級寿司店もきちんと存在している。
つまり、「手軽に楽しめる寿司」が増えたからといって、「高級な寿司」がなくなったわけではないのだ。
アートも同じである。
楽しむ人が増えることは、むしろ全体の文化を豊かにし、「本物」を求める人も育てるのだ。
情報をオープンにすることで市場は広がる
アートをもっと広めるには、情報を開示することが必要である。
どんな思いで描いたのか、どういう技法を使っているのか、どこで買えるのか──それをやさしい言葉で説明すれば、アートはもっと身近になる。
オンライン販売やアートフェアなど、アートの世界は「買いやすさ」でも進化している。
情報を出すことをおそれず、むしろ積極的に発信することが、アーティストにも販売者にも必要なのだ。
情報をオープンにした人が、これからのアート市場をひらいていく。
アート市場の未来は「ゆっくり、でも確実に」広がる
世界のアート市場は、これからも着実に広がっていく。
なぜなら、アーティストになりたい人が増えているし、デジタル技術によって制作がしやすくなっているからだ。
作家同士が切磋琢磨し、自分のスタイルや物語をもって市場に出てくる。
そして、その動きに合わせて、作品を買う人たちも変化している。
投資として買う人、応援として買う人、純粋に気に入ったから買う人──そのどれもが、市場を支える大切な存在なのである。
もちろん、景気や社会情勢に左右される部分はある。
けれど、アートは洋服や家電のように使って終わるものではない。
長く残り、文化として価値が育っていくものである。
タピオカはいつか消える。でも、アートは残る。
そして今、日本のアート市場は、本当の意味で根づいていくチャンスを迎えている。
それを支えるのは、作家だけではない。見る人、知る人、買ってみたいと感じるすべての人なのである。